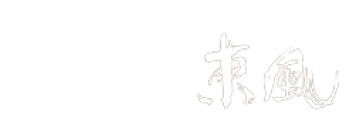木を深く知り、愛情をもって木を扱う

わたしたちがつくる「石場建て伝統構法の家」には、欠かせない素材があります。
それが 木 です。
木とともに生き、木とともに家をつくる。
そのためには、まず木を深く知ることが欠かせません。
私たち東風では、構造材として100年~150年ほど育った国産の杉や桧を主に使っています。
けれども、その木が現場に届くまでには、何十年、あるいは何世代にもわたる営みと、山と向き合う人々の手仕事があります。
苗木を植え、山を育てる林業家。
伐採された木を山から運び出す運搬業者。
丸太を製材する製材所の職人たち。
それぞれの仕事には、山の気配、木の重み、刃物の音、そして人の知恵と誇りが息づいています。

東風ではこれまで、多くの現場に立ち会い、その仕事ぶりをカメラに収めてきました。
このページでは、私たちが実際に見て、聞いて、感じてきた「木が家になるまで」のプロセスを、動画でご紹介します。
家づくりを考える方はもちろん、木や自然の世界に関心のある方にとっても、きっと発見のある映像だと思います。
どうぞ、五感をひらいてご覧ください。
300年の耐久性がある木をつくるために必要なこと
東風が手がける石場建て伝統構法の家では、「300年後まで建物を支える」ことを前提に素材を選んでいます。
そのために、何より大切なのは、木の品質です。
私たちは今から約20年前、現代においては誰もその答えを知っている人がいない疑問について、深く自問自答しました。
それは、300年以上の耐久性を持つ木材とはどういうものか? ということ。
何度も自問自答した結果、至った結論は以下の通りです。
今、築300年以上を経ている建物に使われている木材と同じ条件でつくられた木であれば、その実績から300年以上の耐久性があると言えるのではないか、と。
では300年以上前に、木材はどうやってつくられていたのか?
これは今となっては誰もわかりません。
しかし現代と違って重機もチェーンソーもなく、自然の法則に従って人力や馬の力だけで山から木を出していた先人たちは、以下のような当たり前のことをきちんと守って木をつくっていたはずです。
1. 伐採は木が水を吸い上げるのを止め、水分量が少なくなった時期=伐り旬(晩秋~初冬)に行う
2. 伐採した後は、木を軽く(=運びやすく)するために、数か月間の葉枯らし(はがらし)乾燥を行う
3. 出材後は人工乾燥ではなく、2年以上の天然乾燥を行う
東風で実際に行った葉枯らし乾燥の写真をご覧ください。
下の写真は11月に伐採した樹齢110年の杉の木を、葉をつけたまま4か月間山の斜面に放置し、3月に撮影した写真です。

青丸印の部分、枝がまだ青々しているのがお分かりになると思います。
これは伐採されて4か月経っても、まだ幹の中に残った水分で木が光合成し続けていることの証拠です。
次に木口(こぐち)面の拡大写真をご覧ください。
左が伐採直後(11月)の写真、右が4ヶ月葉

全体的に木口面の色が変色しているのがわかると思います。
伐採直後は鮮やかな色だったものが、4ヶ月葉枯らしすると乾燥して水気が無くなり、くすんだ色になっています。
明らかに木の細胞内部の状態は、伐採直後と葉枯らし後とでは異なっているはずです。
東風ではこのように山で葉枯らし乾燥させた後、最低2年以上はゆっくり天然乾燥させてから使います。
ところが、現在流通している木材は、以下のような条件で生産されています:
・年中いつでも伐採し、適切な伐り旬(きりしゅん)を守っていない
→ 重機が使えるので、木が重くても問題なく搬出できるから
・葉枯らし乾燥を行わず、伐採後すぐに玉切り
→ 葉枯らし乾燥を行うと、森林内部で木が折り重なり、搬出にとても手間がかかる。
・出材後、早く製品化するために3週間程度で人工乾燥させる
→ 木をサウナのような高温の乾燥炉に入れ続け、強制的に水分を飛ばします。
このような木材では、300年もの耐久性を保つとは断言できません。
なぜなら、300年前に建てられ現在まで使われ続けている木造建築物の構造材のつくり方とは違う=300年の実績がないからです。
パッと見た目は300年前の木材と同じかもしれませんが、細胞内部の状態はどうなのか?
100年経った後、現代の木材が本当に問題ないのか?とは誰も断言できません。
だからこそ東風で石場建て伝統構法の家を新築する際は、林業家に直接依頼し、伐採・葉枯らし乾燥・出材のすべてを見届けた木材だけを使うことを、家づくりの前提としています。
木の命に触れる:伐採の現場から
たとえば、奈良県川上村で撮影した、樹齢140年の吉野杉の伐採の映像をご覧ください。
この木を伐ったのは、代々吉野で林業を営む福本林業の4代目、福本雅文さん。
15年以上にわたり、東風の家づくりを支えてくれている信頼の林業家です。
この映像からは、単なる「作業」ではなく、一本の木を伐るという行為に込められた敬意と集中が、きっと伝わってくるはずです。
樹齢140年 吉野杉の伐採 / 140 years old Yoshino cedar felling in Japan
続いて、同じく福本さんによる、樹齢100年の伐採の様子もご覧ください。
山と木を理解するために
福本さんたちと山に入り、学んだことは数えきれません。
「山」とひとことで言っても、そこには 人工林 と 天然林 の違いがあり、それぞれに手入れの仕方や木の性質が異なります。
こうした基本的な知識は、家づくりに関わる私たちにとって欠かせない土台です。
簡単にまとめた動画を用意しましたので、ぜひご覧ください。
人工林と天然林の違い
木は伐って終わりではない
伐採が終わったら、木を山から運び出す「出材(しゅつざい)」の工程が始まります。
険しい山の中では、大型トラックが近づけないこともしばしば。そんなときは、架線(ワイヤー)を張ってキャレージで運搬したり、場合によってはヘリコプターも登場します。
実際の様子を映した映像をご覧ください。
架線での出材作業の様子
さまざまな事情で架線が貼れない場合などは、ヘリコプターを使って出材します
ヘリコプターによる出材の様子
木の命を活かす、ということ
わたしたちが日々向き合っているのは、「資材としての木」ではなく、「生きてきた木の命」です。
その命をどう受け継ぎ、いかに次の世代へと残していくか。
家をつくるということは、自然と文化をつなぐ行為そのものだと思います。
山の風、木の香り、伐るときの緊張感。
映像を通じて少しでも感じていただけたなら、幸いです。
このセクションのコンテンツ一覧
・木造でも遮音できます。集合住宅、遮音室、二世帯住宅、古い旅館など
・近畿圏外から、東風に設計の依頼をご検討下さっているみなさまへ
・金物を使わない構造体の意図とは?(執筆中)
・石場建て伝統構法と、高気密・高断熱の両立について(執筆中)
・良い職人、良い設計者を育てるということ(執筆中)