
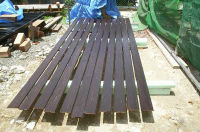

左 : 1F外壁面に張る杉板(赤身)の表面に塗装をしているところです。
作業をしているのは施主のW氏です。
今回はドイツのLivos(リボス)というメーカーの外部塗装用塗料を使いました。
ハケで塗料を塗った後、すぐにウエスで拭き取って仕上げます。
右 : 塗装した板を乾かしているところです。
Livos(リボス)社の塗料は植物油製なので乾燥しにくく、乾かすのに時間がかかります。
下 : 塗装しあげた板の拡大写真です。
拭き取りをしているため、杉の木目がくっきりと浮き上がっています。
キレイでしょ?














