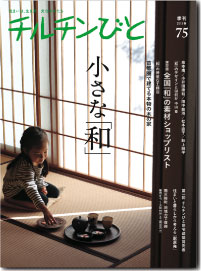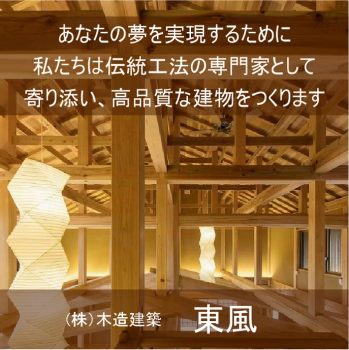兵庫県丹波市において昨年から工事を進めてきた、H様 + Y様邸2世帯住宅となる、築80年古民家再生工事が完成しました。
建築主様のご厚意により、完成見学会を開催させて頂けることになりましたのでご案内致します。
施工は(有)すぎもと工務店様が手がけて下さいました。
こちらのお宅の再生工事前の課題は、以下のようなものでした。
● 親世帯と子世帯が同居できる間取りにしたい
● 冬は寒く、暗い室内を、暖かく・明るく快適に過ごせるようにしたい
● 築後80年を経過した家を、これからも長く住み続けられるように手入れをしたい
(耐震補強・通風・湿気の問題など)
お父様と息子様はお二人とも農家。
生活と農が密接に結びついているご家庭です。
今回の再生工事にあたって、上記の課題は以下のように改善しました
○ これまでは居室として使えなかった2階の断熱性能を高めて
居住性を改善し、2階全域を子世帯の生活空間とする
○ 大型の薪ストーブを導入し、主な生活空間の2/3を 1台で
暖めることで、厳しい冬を快適に過ごせるようにする
○ 傷んでいた構造部材は補強・入替を行い、土壁を増設し、
耐震性能を向上
何点か写真をご用意しましたのでご覧下さい。

画像1
建物外観/外壁は杉板を新たに張り替え、
開口部にはアルミサッシ(ペアガラス)を設置しました
画像2.
2階居室/天井が低くて圧迫感のあった2階の納戸は、
天井を取り払って開放的にし、屋根下に遮熱層を設けて
快適な温熱環境を実現しました
画像3.
家族全員が集う居間は間接照明を設置して
温かな雰囲気に仕上げました
画像4.
洗面化粧台は、木とタイルでかわいい感じにつくりました
画像5.
玄関土間に大型の薪ストーブを設置しました。
これ1台で家の約2/3が快適に温まります
画像6.
床板には杉の厚板(30mm)を使用しています
見学会当日は、住まい手であるY様ご夫妻から、
住み心地や再生工事前後での生活の変化などについて、
直接お話を伺うことができる大変貴重な機会です。
すでに建物内では建築主様の新生活が始まっているため、
1時間あたり1組限定で見学して頂きます。
先着順で定員(8組)に達し次第、受付を締め切らせて
頂きますので、どうぞお早めにお申込み下さい。
(完全予約制です)
【開催日時】 4/14(日) 10:00-17:00
(最終組入場16:00)
お申込の際、来場希望時間を必ずご記入下さい
【開催場所】 兵庫県丹波市内
※お申込頂いた方に住所をお送りします
4/20(土)、静岡市葵区で標高1700mの天然林を全身で感じるためのツアーを行います。
地元の林業家に案内して頂き、森の中の植物や生態系のことなど、
いろんな話を聴きながら、1日森の中を歩いて標高1700mの天然林
を目指します。
天然林の中に身をおいてみて初めてわかる素晴らしい感覚を、
ぜひ体感していただきたいと思って企画しました。
下の写真は、ブナの木立を見上げたものです。

こんな景色を観に行きたい方はこちらからアクセスしてみて下さい。